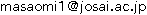|
所属 |
現代政策学部 社会経済システム学科 |
|
職名 |
准教授 |
|
連絡先 |
|
|
外部リンク |
学内職務経歴 【 表示 / 非表示 】
-
城西大学 現代政策学部 社会経済システム学科 准教授
2020年04月 - 現在
-
城西大学 現代政策学部 社会経済システム学科 助教
2018年04月 - 2020年03月
学外略歴 【 表示 / 非表示 】
-
群馬県立女子大学 講師
2023年04月 - 現在
-
高崎経済大学 講師
2022年09月 - 現在
国名:日本国
-
学習院女子大学 講師
2022年04月 - 現在
国名:日本国
-
青山学院大学 講師
2016年04月 - 2016年09月
国名:日本国
-
藤岡市役所 職員(事務系)
1999年10月 - 2018年03月
国名:日本国
所属学協会 【 表示 / 非表示 】
-
観光学術学会
2025年03月 - 現在
-
文化経済学会<日本>
2013年06月 - 現在
-
日本文化政策学会
2010年04月 - 現在
-
文化資源学会
2007年08月 - 現在
研究経歴 【 表示 / 非表示 】
-
革新自治体の文化行政を問い直す
その他の研究制度
研究期間: 2017年06月 - 現在
1970年代以降、登場した革新自治体は、文化行政の領域においても重要な影響をもたらした。そのうちの一つである埼玉県とモデル自治体として取り上げられた基礎自治体の分析を通じて、文化行政とは何だったのかを問い直すとともに、その後に登場した文化政策の意義について考察を試みる。
-
その他の研究制度
研究期間: 2016年04月 - 現在
日本の高度成長期において開発と遺跡の保存は二項対立的関係にあった。市民運動としての遺跡の保存運動は、経済的発展を望む地域住民の圧力に屈する形でとん挫する。しかし、それは運動の失敗を意味するものではなく、やがて遺跡保存と地域開発を両立させる出発点であった。本研究は今日のまちづくりにおける文化財保護運動の意義を検証することをもって、今日の文化政策総体を問い直すことを目的とする。
-
その他の研究制度
研究期間: 2008年04月 - 現在
文化財保護行政、特に埋蔵文化財行政は市民の直接的参加は困難な状況に置かれている。1962年から野尻湖で市民の参加によって実施されてきた「野尻湖発掘」の事例分析を通じて、市民参加型発掘調査が生み出す参加者の学び、調査における多様な視点の取り込みの先に、地域社会が学術調査を支える文化の醸成を見出す。このことをもって、今日の文化財保護行政における市民参加の社会的意義を問い直す。
論文 【 表示 / 非表示 】
-
クラウドファンディングを契機とした文化遺産保護を支える支援者創出の可能性 査読あり
土屋正臣
文化経済学 22 ( 1 ) 17 - 25 2025年03月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌)
-
クラウドファンディングによる文化遺産の持続的な保護の可能性
土屋正臣
城西現代政策研究 17 ( 2 ) 1 - 13 2024年03月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)
-
戦後日本における「文化」と「観光」の位置関係の変容―「文化観光」を手掛かりとして―
土屋正臣
城西現代政策研究 16 ( 2 ) 59 - 70 2023年03月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)
-
1970・80年代の文化行政に対する文化財保護の立ち位置に関する試論 : 埼玉県を事例として 査読あり
土屋正臣
文化政策研究 ( 14 ) 126 - 137 2021年04月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本文化政策学会
-
城西大学における学芸員養成課程設置の意義-文化政策としてのミュージアムの可能性を踏まえて-
土屋正臣
城西現代政策研究 14 ( 2 ) 85 - 102 2021年03月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要) 出版者・発行元:城西大学現代政策学部
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
文化という名の開発―再生産される「豊かな未来」
土屋正臣( 担当: 単著)
春風社 2025年05月
-
Cultural Heritage in Japan and Italy Perspectives for Tourism and Community Development
( 担当: 共著)
2024年04月
-
自治体文化行政レッスン55
小林 真理 , 鬼木 和浩, 土屋 正臣, 中村 美帆 ( 担当: 共著)
美学出版 2022年02月 ( ISBN:978-4-902078-70-1 )
記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
自治体文化行政に携わる行政職員にとって必要な知識を、現場の疑問に答えるべく基礎から応用までまとめた全自治体必携の書。指定管理者や文化芸術団体等の多様な関係者が、文化行政のリアルを学ぶのにも役立つ一冊。
-
法から学ぶ文化政策
小林真理,小島立,土屋正臣,中村美帆( 担当: 共著)
有斐閣 2021年11月 ( ISBN:978-4-641-12630-5 )
記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
政策のよりよい運営には法の理解が欠かせない。これからの担い手が知るべき文化政策関連法の全体をわかりやすく案内する,画期的なテキスト。具体的な現場の動きから抽象的な理念や枠組みまで,図解とともに丁寧に見通す。文化政策にかかわるすべての人に役立つ1冊。
-
新時代のミュージアム:変わる文化政策と新たな期待
河島伸子,小林真理,土屋正臣( 担当: 共著 , 範囲: 第5章 地域に生きるミュージアム──価値提供のあり方,第8章 ミュージアムとまちづくり──長野県茅野市内のミュージアム群)
ミネルヴァ書房 2020年09月 ( ISBN:9784623089741 )
総ページ数:274 記述言語:日本語 著書種別:学術書
現在、日本には公立・私立あわせて多数のミュージアムがある。ミュージアムの社会的役割や運営の仕方が問い直されるいま、地域社会との関係や来館者への魅力の訴えといった諸課題を取り上げ、これからのあるべき姿を提示する。
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
文化観光を通じた文化遺産「らしさ」の妥当性はいかにして、誰によって決定されるか ―城郭の“品位”をめぐるステークホルダー間の調整
土屋正臣
観光学術学会第14回大会 2025年07月 観光学術学会
開催年月日: 2025年07月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:琉球大学
-
文化観光政策におけるメディエーターの役割
土屋正臣
2024年度日本文化政策学会第18回年次研究大会 2025年03月 日本文化政策学会
開催年月日: 2025年03月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:八戸市美術館
-
土屋正臣
第2回文化観光セミナー –ファンと共創する文化観光– 2025年03月 文化庁
開催年月日: 2025年03月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(基調)
開催地:熊本城ホール
-
文化政策としての市民参加型遺跡調査を考える─最近の事例から―
土屋正臣
海洋総合知オンライン・シンポジウム 海洋文化遺産と市民科学 2025年01月 神戸大学海洋文化遺産プロジェクト 総合知手法創出チーム
開催年月日: 2025年01月
記述言語:日本語 会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)
開催地:オンライン
-
土屋正臣
文化観光セミナー 2024 ‐文化観光が目指す未来‐ 2024年08月 文化庁
開催年月日: 2024年08月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(基調)
開催地:京都文化博物館
その他研究活動 【 表示 / 非表示 】
-
城西大学水田美術館特別展「震災後10年のいま、これから」
2022年02月 - 2022年03月
震災の記憶が地域の復興にどのような貢献なすのかという問いに基づき、リアス・アーク美術館の写真を中心に展覧会を実施した。また、オンラインでの講演会や学生による解説などのワークショップを展覧会会期中に行った。
-
『フランス都市文化政策の展開:市民と地域の文化による発展』(長嶋由紀子著、美学出版、2018年)
2020年06月
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
文化観光のエコシステム成立に係るメディエーターの役割
研究課題/領域番号:24K15542 2024年04月 - 2027年03月
基盤研究(C)
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
平成の日本の文化政策と文化政策関連研究の検証
研究課題/領域番号:23H00589 2023年04月 - 2028年03月
基盤研究(B)
担当区分:研究分担者
-
文化政策における文化財保護行政の位置:70年代以降の埼玉県文化行政の分析
研究課題/領域番号:19K13035 2018年04月 - 2021年03月
若手研究 若手研究(S)
文化芸術基本法制定、文化財保護法改正など、文化財の活用が議論される中で、現実には文化施設の統廃合が行われ、文化行政の系譜は必ずしも肯定的に捉えられていない。文化行政の本質を捉え、今後の文化政策における文化財保護の道筋を模索することが求められている。そこで、革新自治体における文化行政のトップランナーであり、かつ文化財保護行政が文化行政の礎を構築していった埼玉県を事例として分析し、文化財保護行政が文化政策総体に与えた影響について明らかにすることが、本研究の目的である。
共同研究実施実績 【 表示 / 非表示 】
-
新たな価値創造をする文化遺産活用の国際共同研究 ユーザー関与度深化、地域作りの視点
2019年10月 - 現在
独立行政法人日本学術振興会 国際共同研究
河島伸子、矢ケ崎紀子、李知英
-
世界史からみる銘仙:デジタルアーカイブ 化と国際発信
2019年04月 - 現在
国内共同研究
担当授業科目 【 表示 / 非表示 】
-
政策ゼミナールⅡ
2020年04月 - 現在
-
日本文化論B
2019年09月 - 現在
-
文化政策B
2019年09月 - 現在
-
文化政策A
2019年04月 - 現在
-
政策ゼミナールⅠ
2019年04月 - 現在
担当経験のある科目(本学以外) 【 表示 / 非表示 】
-
アーツ・マネジメント
機関名:高崎経済大学
-
文化行政法
機関名:青山学院大学総合政策学部
-
日本文化政策論Ⅰ・Ⅱ
機関名:学習院女子大学
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
文化庁 令和7年度 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業1次公募審査委員
2025年04月 - 2025年05月
団体区分:学協会
-
文化庁 令和6年度 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業2次公募審査委員
2024年09月
団体区分:政府
-
文化資源学会理事
2024年07月 - 現在
団体区分:学協会
-
文化庁 令和6年度 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業1次公募審査委員
2024年06月
団体区分:政府
-
文化庁 「日本遺産魅力向上事業」に係る技術審査専門員
2023年03月 - 2023年04月
団体区分:政府
社会貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
海洋教育パイオニアスクール講師
役割:講師
千葉県立天羽高等学校、第一海堡 2025年11月
対象: 高校生
種別:出前授業
-
令和7年度 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業伴走支援(コーチ、有識者)
役割:助言・指導, 運営参加・支援
文化庁 2025年06月 - 2026年03月
-
令和6年度 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業伴走支援(コーチ、有識者)
役割:助言・指導, 運営参加・支援
2024年06月 - 2025年03月
対象: 社会人・一般, 企業, 行政機関
-
浦和麗明高校高大連携
役割:講師
2020年06月
対象: 高校生
-
大田区文化振興推進協議会 文化施設のあり方分科会委員
2018年05月 - 2018年08月
・大田区文化振興推進協議会 文化施設のあり方分科会委員(学識委員)
・大田区文化振興プランを改定するにあたり、区内の文化施設(ホール、展示・鑑賞施設)のあり方を検討することは必須と考えられる。そのため、『大田区文化振興推進協議会』の下に施設のあり方を検討する分科会を設置し、具体的な検討を進める。
・検討予定の内容
① 文化施設の役割・機能・体系の整理。特に、センター館としての郷土博物館の役割の明確化。
② 大田区内の文化資源を整理し、民間の文化施設等との連携や、新たに必要となる文化施設の提言。
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
赤字続きの熊本城、「自主財源の確保」狙い新たな活用策…「ファン増やしたい」と寄付の増加にも期待 新聞・雑誌
読売新聞 読売新聞 2025年04月
執筆者:本人以外
-
能登の文化財復興支援が苦戦…国予算不足、文化庁CFは目標額の1割 新聞・雑誌
読売新聞 2024年06月
執筆者:本人
-
なぜ?地方が注目!メタバース美術館
NHK 2023年08月